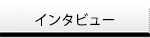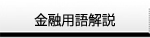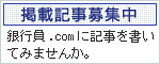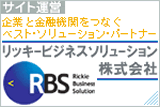[室町紀行 第ニ話] 紅茶に関するとりとめもない考察 | 七十七銀行 東京事務所 田畑 卓治 氏
 七十七銀行 東京事務所
七十七銀行 東京事務所 田畑 卓治 氏
1986年4月 七十七銀行入行。以降 法人営業部法人営業課長、郡山支店長などを経て 2009年6月 東京事務所長(現職)
どちらかといえば、コーヒーよりも紅茶が好きだ。
時に金色にも見える透明な琥珀色、心穏やかにするあまやかで馥郁たる香り、そして何よりもそのすっきりとした味わい。ティーブレイクとは良く言ったものである。
だからといって自分で好みの茶葉を探し求め、淹れ加減の試行錯誤を繰り返し、自らの究極の一杯を追求するなどということはしない。自分の味覚や嗅覚、センスの平凡なることは自身が一番良く理解しており、それよりは、「紅茶専門店」などという看板に無計画に誘われ、思いがけず好みの一杯に巡り合うことの至福の方を旨としている。
そんな訳からでもないが、最近、新聞の書評とその刺激的な訳名に惹かれ、「紅茶スパイ」という書を読んだ。
時は19世紀半ば。産業革命をいち早く成し遂げ、帝国主義による植民地政策を強力に推し進めていたイギリスでは、国内での都市化が急速に進展し、幅広い層で紅茶を飲む習慣が形成されつつあり、清王朝が支配する中国から大量の茶葉を輸入していた。
当時、イギリス植民地政策の経済的側面を担っていたのが、かの有名な東インド会社であるが、同社は、イギリスの植民地であったインドへ自国の綿布製品を輸出し、かわりにインドで生産させたアヘンを購入し、そのアヘンを中国へ売却することで茶葉の代金を精算するという「三角貿易」のシステムを確立していた。
しかし、このシステムは、中国が自国でアヘン生産を開始したら、たちまちのうちに瓦解する。アヘンの生産と精製技術がさほど難しくないのに対し、高級茶葉の生産とその精製技術は、中国が国外への流出を固く禁じ、未だ謎のヴェールに包まれたままであった。
そこで、東インド会社は、ヒマラヤ山脈の山麓で、イギリス産茶葉の生産を実現するべく、中国の高級茶葉の苗と種子を手に入れ、さらにはその精製技術を持つ技術者をヘッドハントするため、中国の国内事情に精通したプロのプラントハンターに、このミッションを依頼するのである。
このミッションの成否は、現代における紅茶の一大産地が、インドのダージリン地方やアッサム地方、セイロン島(現在のスリランカ)などにあることをみれば明らかであろうが、今や世界第二位の経済大国となった中国が、レアアースの権益独占を目指し、アフリカの新興国に対する積極投資や資金支援を行っていることが、何故か二重写しのように見えて仕方がない。
人間の営みが、地球が育む動植物の命の連環の中にあり、また、自然界からもたらされる資源の活用を必要とするなら、いかに科学技術が進歩しようともいずれ歴史は繰り返すと、「一杯の紅茶」から思い至るのは、あまりにも飛躍し過ぎであろうか。
(2012/4/3 掲載)